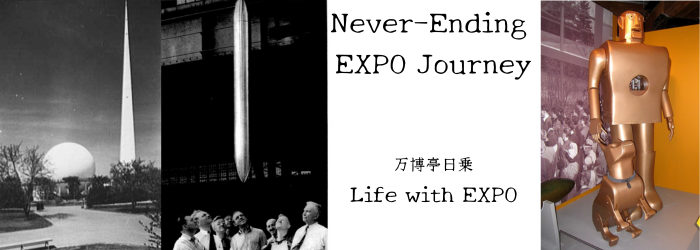ジャン=フランソワ・ミレーが「農民画家」となるまで
オルセー美術館には、19世紀万博で活躍した数多くの作家の名品が多数収蔵されている。
日本人でも知らない人はほとんどいないだろうジャン=フランソワ・ミレー(Jean-François Millet, 1814-1875)の作品も収蔵されている。
ミレーといえば、バルビゾン派の画家として有名である。
生まれは1814年、フランス北西部のノルマンディー地方のグリュシー村である。
20歳代前半、父の死後、農業を継ぐつもりだったが、祖母の強い勧めもあり、画家になる決意を固めたという。
そして、1837年、パリへ上京し、国立美術学校(エコール・デ・ボザール)でポール・ドラローシュに師事することとなった。
1840年にはサロン(官展)に初入選を果たしている。この時は肖像画であった。
そして1849年、パリでのコレラの流行を避けるため、パリ郊外のフォンテーヌブローの森の近くの村バルビゾンに移住し、この地でテオドール・ルソーらと共に「バルビゾン派」の主要メンバーとなった。
バルビゾンでの生活を通じて、農民の労働と大地に根ざした生活を、宗教的な崇高さをもって描き、ミレーは「農民画家」と言われるようになったのである。
筆者も以前バルビゾンを訪れたことがある。
今でも農村そのままであり、ミレーの絵を見ているような景色が周囲に広がっていた。
1867年パリ万博とミレー
じつは、ミレーは1855年パリ万博でも『接ぎ木をする農夫』を出展した。しかし、このときは特に評判にもならず終わっていた模様である。
しかし、12年後のパリ万博ではミレーの名声は相当に高まっていたようで、様子が違った。
1867年パリ万博では、万博美術展会場内にミレーに一室が与えられたのである。
その中で『落穂拾い』(1857年)や『晩鐘』(1857-59年)など、われわれになじみの深い作品も含め9点が展示されることとなった。
『落穂拾い』も『晩鐘』も、万博で展示された作品だったのである。

オルセー美術館に展示されている
ミレー『落穂拾い』
photo©️Kyushima Nobuaki

オルセー美術館に展示されている
ミレー『晩鐘』
photo©️Kyushima Nobuaki
その2作品とも現在、1900年パリ万博のために建てられたオルセー駅の駅舎を活用したオルセー美術館の中で、展示されているのである。
そう思いながら実物・本物の『落穂拾い』や『晩鐘』を目の前にするとなんだか158年前の万博の様子がじんわりと思い起こされてくるのである。