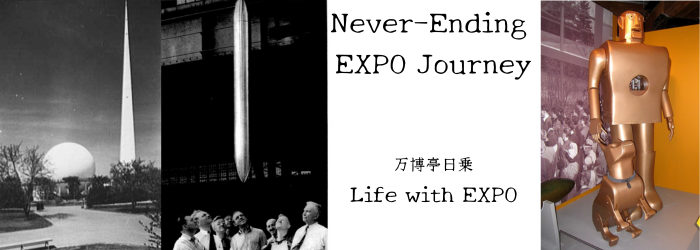第77回正倉院展
奈良の奈良国立博物館で、「第77回正倉院展」が開催中である。
開催期間は、2025年10月25日(土)~11月10日(月)。
その初日に秋の奈良を訪れてみた。

第77回正倉院展サイン
photo©️Kyushima Nobuaki

第77回正倉院展開催中の国立奈良博物館
photo©️Kyushima Nobuaki

第77回正倉院展開催中の国立奈良博物館
photo©️Kyushima Nobuaki
以前は予約制ではなかったので長時間並ぶ覚悟が必要だったが、最近は予約制なので、予約時間の少し前に行けば10分ちょっと列に並ぶだけで入ることができる。
今回の「第77回正倉院展」のホームページによると、今回の内容は以下の通りである。(抜粋)
一方、ほとけへの捧げものを収めた「黒柿蘇芳染金銀山水絵箱」(中倉156)など、技巧を凝らした祈りの宝物を通じて、仏教をよりどころとした当時の人々の心にも近づくことができるでしょう。
宮内庁正倉院事務所による最新の宝物調査の成果も織り交ぜながら、豪華なラインナップで開催する今年の正倉院展を、ぜひともご堪能ください。
会場内は写真撮影禁止なので作品の写真をお伝えすることはできないが、周囲の雰囲気の写真はアップしておこう。

第77回正倉院展サイン
photo©️Kyushima Nobuaki

第77回正倉院展 会場内サイン
photo©️Kyushima Nobuaki

第77回正倉院展 会場内サイン
photo©️Kyushima Nobuaki
予想通り多くの人で賑わっていた。
数々の宝物はさすがに素晴らしく、わざわざ東京から来てみる価値はある。
以前より随分外国人観光客が増えた気はするが、それでもまわりののんびりした鹿にもいやされて奈良の昔に戻ったような気分にもなる。

奈良国立博物館周辺の様子
photo©️Kyushima Nobuaki

奈良国立博物館周辺の様子
photo©️Kyushima Nobuaki
「奈良博覧会」のはじまり
さて、この正倉院展だが、もともとは「奈良博覧会」として始まった。
第一回目の「奈良博覧会」は1875年(明治8年)、奈良の東大寺大仏殿および回廊を会場とし、官民共同で設立された「奈良博覧会社」(1874年創立)が主催して行われた。

東大寺大仏殿
photo©️Kyushima Nobuaki
会期は1875年4月1日から6月19日までの約80日間。
この博覧会で、史上初めて、正倉院宝物約220件、合計1,700点以上が一般に向けて公開されたのである。
聖武天皇・光明皇后ゆかりの品々が展示され、人々に大きな感銘を与えた。
今回の「正倉院展」で展示されている、名香「蘭奢待」として世に知られる「黄熟香」もこの博覧会で展示されたと記録されている。
また、他にも、法隆寺や東大寺などの寺宝、各種特産品、宮内省から拝借した御物、模写や模造事業など、多岐にわたる内容が展開された。
この博覧会は約17万人を集めたという。
さて、この「奈良博覧会」は1875年(明治8年)の第1回から、1894年(明治27年)まで少なくとも18回開催された。(ただし、途中開催されなかった年もあった)。
1894年に「奈良博覧会」は一旦終了することになったのである。
「正倉院展」の始まり
そして第二次世界大戦直後の1946年(昭和21年)に「正倉院展」が初めて開催されることになるのである。
第1回目の「正倉院展」は奈良帝室博物館(現在の奈良国立博物館)で開催された。そして、その後3回の東京開催を除き、ほぼ毎年奈良で開催されているのである。
そして今回第77回を迎えたというわけである。
ちなみに、奈良国立博物館のホームページによると、次のようにある。
パリ万博との関係
上記のように、やはり、奈良博覧会も奈良国立博物館も1867年パリ万博が契機となったものであった。
ことほどさように、万博はさまざまな我々の身近のものを生み出してきたのである。