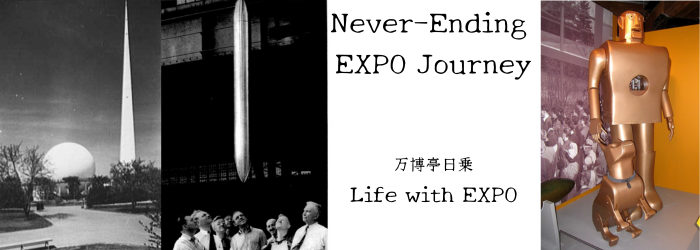「温室」から「美術館」へ
さて、<165>でご紹介した、ナポレオン3世の指示で1853年に建てられた、チュイルリー庭園の巨大なオレンジの温室は、1921年に始まった改装工事で美術館へと変貌することになる。

オランジュリー美術館外観
photo©️Kyushima Nobuaki
このきっかけとなったのがクロード・モネの連作『睡蓮』である。
モネの『睡蓮』と万博の関係については、
などでもご紹介したが、要約すると、
ということになる。
モネの『睡蓮』ももともとは1889年パリ万博がきっかけになったのである。
さて、そのモネは、第一次世界大戦の終結を記念して、自分の連作『睡蓮』を国家に寄贈することを申し出たのである。
モネは、その際、絵画が自然光の下で展示されることを強く要望し、それを叶えるために、この温室が改装されることになったのである。
そして1927年、オランジュリー美術館が正式に開館した。

オランジュリー美術館外観
photo©️Kyushima Nobuaki
モネの構想に基づき、自然光が降り注ぐ楕円形の2つの部屋が作られ、そこに8枚の巨大な『睡蓮』の絵画が展示された。

オランジュリー美術館 モネの「睡蓮の間」
photo©️Kyushima Nobuaki

オランジュリー美術館 モネの「睡蓮の間」
photo©️Kyushima Nobuaki

オランジュリー美術館 モネの「睡蓮の間」
photo©️Kyushima Nobuaki

オランジュリー美術館 モネの「睡蓮の間」
photo©️Kyushima Nobuaki

オランジュリー美術館 モネの「睡蓮の間」
photo©️Kyushima Nobuaki

オランジュリー美術館 モネの「睡蓮の間」
photo©️Kyushima Nobuaki
モネ以外の作品も追加される
1950年代後半、美術商であったジャン・ヴァルテールとポール・ギヨームのコレクションが美術館に寄贈された。
これには、セザンヌ、ルノワール、ピカソ、マティス、モディリアーニなど、印象派や後期印象派の重要な作品が含まれていた。
1960年代にこれらの作品を展示するための大規模な改装工事が行われた。
しかし、この改装工事により、モネの間には自然光が入らなくなってしまった。
そこで1999年〜2006年、再び大規模な改修工事が実施された。
この改修で、以前の改修で閉鎖されていた自然光を取り込む窓が再び開けられ、モネが意図した展示方法が復活した。
また、地下に展示スペースが設けられ、ヴァルテールとギヨームのコレクションがそこに集約されることになった。
これにより、1階は『睡蓮の間』、地下はその他のコレクション、という現在の展示構成が確立したのである。
楕円形の2つの部屋で構成された「睡蓮の間」
ここには次のような解説パネル(日本語もあり)が掲げられている。
モネは形やボリューム、配置、場所、パネル間の空間、開放的な展示室で来館者が自由に作品を鑑賞出来る事、太陽光など、あらゆる点を予測していました。
2024年10月5日から2025年2月11日まで東京の国立西洋美術館で開催された「モネ 睡蓮のとき」展にもこのオランジュリー美術館の「モネの間」のような楕円形の展示会場による展示が行われていた。
この展覧会については、
<107>「モネ 睡蓮のとき」展 ー モネが睡蓮を「発見」した万博とは
でご紹介した通りである。
しかし、やはり本当のパリのオランジュリー美術館の「モネの間」の体験はその時の展示とは比較できないほど素晴らしい。
筆者は過去何度もこのオランジュリー美術館を訪れているが、改修工事後に訪れたのは今回が初めてだった。
この改修工事によって可能になった、モネの遺志のとおり降り注ぐ自然光の中で『睡蓮』を味わう、というのは、やはり現地に行かなければ味わえない貴重な体験といえよう。